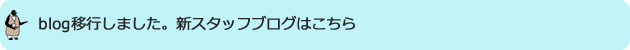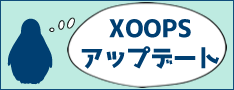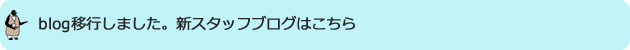
スタッフブログ

画面の概要を書くことになりました。
こういう場合、最近はエクセルの縦横罫を狭めにし、方眼紙のようにしてから作ることが多いのですが今回はまだ内容が決まり切っていないので軽く手書きでいいという状態です。
昔はフルスカップという用紙があって手書きで書いたんだけどな、と思いつつ時間がなかったので画面のハードコピーをとって画像処理ソフトで加工をして書類を作りました。画像加工ソフトもちょうどいいのが見つからなくて思ったよりたくさんの時間がかかってしまいました。
こういう時、フルスカップがあったら便利なので検索してみましたが売っているところはありません。
フルスカップとはレポート用紙のように1枚ずつ切り取れる用紙で縦横罫が5ミリほどのものです。ラインはブルーなのでコピーしたときに出ないようになっています。用紙もトレーシングペーパーのように薄く書きやすいものでした。
考えてみると当時も会社のロゴ入りのものが備品としておいてあったので自分で買ったことはありません。当時、というのが20年以上前というのが問題なような気がしますが…
どなたかフルスカップを売っているところ、知りませんか?
今から覚えるXen part1. Xenについて
前回はXenについて簡単に説明しました。いつまでも概要について説明するよりは実際に動いているものを見た方が理解が早いので早速イン
ストールに挑戦してみましょう。
part1.の後半で紹介したように、インストールする環境はUbuntu Linuxになります。SUSEやFedora、CentOSに関するXenのインストール報告
は多いのですがUbuntuで運用しているという人があまりいないのであえて挑戦です。他のディストリビューションを利用している人は各自>でインストール方法を検索してください。
インストール手順はdebパッケージをインストールするだけなので簡単です。aptitude search xenで検索してそれっぽいパッケージをイン>ストールします。具体的には以下のパッケージになります。
<br />
-libxen3<br />
-linux-image-xen<br />
-linux-xen<br />
-python-xen-3.2<br />
-ubuntu-xen-server<br />
-xen-docs-3.2<br />
-xen-hypervisor-3.2<br />
-xen-shell<br />
-xen-tools<br />
-xen-utils-3.2<br />
-linux-restricted-modules-xen<br />
あたりをインストールしました。インストールしたXenのバージョンは3.2になります。
これであとはネットワークの設定をしてイメージを作るだけなのですが、残念ながら私がインストールしたカーネルイメージにバグがあっ>たようで、ネットワーク設定がどうやっても認識しませんでした。
Bug #204010 in xen-3.2 (Ubuntu): “networking not working>”
を参考に、ひらのさんという方が作ったイメージをダウンロードしてインストールするとこの問題が解決できます。
ひらのさんのサイトから、自分の環境にあったイメージをダウンロードしま
す。私は今回64bit環境だったのでlinux-image-2.6.24-16-xen_2.6.24-16.30zng1_amd64.debをダウンロード。
<br />
sudo dpkg -i linux-image-2.6.24-16-xen_2.6.24-16.30zng1_amd64<br />
としてインストールしました。
これでインストール作業はすべて完了です。再起動したら、
<br />
sudo xm list<br />
として、Domain-0が見えるかチェックしてください。
次回はネットワークの設定とイメージの作成を行います。
他者からSSHの鍵をもらった場合、そこに書いてあるパスフレーズが複雑で面倒だと思ったことはないでしょうか。
SSHの公開鍵認証は通常、認証前にパスフレーズを入力しますが、SSHの公開鍵認証は、
手元の鍵を手元のパスフレーズで復号化->復号化された鍵をサーバに送信して認証
という手順なので、パスフレーズというのはローカルだけで簡単に変更することができます。
普段からLinuxを使っている方はすでにご存じだと思うので省略しますが、WindowsであればPuTTYに付属のputtygen.exeでパスフレーズを変更することができます。
使い方は簡単で、puttygen.exeに鍵を現在のパスフレーズを入力して読み込ませると、パスフレーズ入力欄があるので、そこを変更して再度鍵を保存するだけです。
ちなみに、パスフレーズ無しの鍵を作る方法もありますが、一応パスフレーズは入れておいたほうがいいと思います。
最近はほとんどが公開鍵認証だと思うので、これで複雑なパスフレーズを覚える必要が無くなります。
是非お試しください。
RYUSでもこのサイト以外に、社内のスタッフとお手伝いしていただいてる方がアクセスする社内サイトをXOOPSでつくって利用しています。
RYUSの社内サイトは非常にシンプルな構成で、
・社外の方も含めて閲覧・投稿できるフォーラム
・スタッフだけが閲覧・投稿できるフォーラム
・案件ごとに、その案件に参加している人だけが閲覧・投稿できるフォーラム
というのが基本になってます。
これに、プラスして、私の予定をみんなが把握できるようにpiCalをいれたり、資料のダウンロードスペースを用意したりして使ってます。
たったこれだけの事なんですが、徐々に役立ってきてます。
■どんな点でよかったのか?
1.書く場所ができた。
情報共有とかナレッジ共有サイトを検討するときに、コンテンツをしっかり整理しようとか、役立つ情報が参照しやすいようにシステム側でなにかしかけをつけようとか、ついつい大がかりに考えすぎてしまうことがあります。
その結果、けっきょく何も手つかずということが少なくないと思ってます。(実際、私はその傾向が非常に強いと思ってます)
とりあえず「書く場所」だけでも用意することで、箇条書き程度でも打ち合わせの議事録を書きためたり、「○○なときは、××してから△△すればいい」というようなことも書きためられるようになってきました。
もちろん見やすいように整理してあるのがベストですが、書いてさえあれば検索でみつけることもできるし、何か聞かれたときも「それならフォーラムに書いてあるからURL送るよ」ですむこともあります。
これ、書いてないと何か聞かれる度に、何回も同じ話をすることになったり、「聞いた覚えがあるけどどうするんだっけなぁ」というときも、相手の時間をもらって、口頭で確認することになってしまいます。
2.書くことで思考が整理されるようになった。
打ち合わせをした後に、できるだけ議事録を社内サイトに書くようにしています。
箇条書き程度の簡単なものですが、書くと思考が整理されるようで、打ち合わせ中には気がつかなかったことに気がついたり、「あれ?結局これって結論でてないな」ということがあるのに気がついたりします。
書くことで思考が整理されるのは実感としてはあったのですが、これまでは意識的に考える時しか実行していませんでした。
議事録を書くというのはこれまであまり重視してこなかったのですが、書くことで新たな発見があるというのがわかったので、これからも続けていこうと思ってます。
というわけで、まだ社内サイトが無いなら、まず書くための入れ物としてXOOPSを導入することを検討してみてはいかがでしょうか

先週末、タイトルと作者に興味をひかれてこの本を買いました。以前読んだ本は硬派のドキュメンタリーという感じでしたのでちょっと意外だなぁと思いました。 内容は仕組み仕事術、にもあるように効率よく仕事をするやり方や一般的な心構え「人から勧められたらとにかくやってみる」というようなこと、「ネタは一度に使わず続編のためにとっておく」などなどなるほどなぁと思うようなことが数多く書かれています。単にラクをしてちゃっかり、というのでもなく、ラクといいつつ実は陰ながらすごく努力するというものでもなく自己啓発本によくあるストイックな感じとは一線を画していて非常におもしろかったです。
以前読んだ同作家の本はこれでした。精神的な病気、という診断で多くの殺人者が社会に復帰する様が描かれていてこちらも興味深い、というか恐ろしい本です。問題は診断基準のあいまいさにあると思われます。